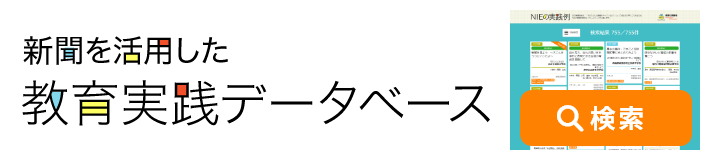“先生”体験から考える
- NIEトップ
- 新聞各社の「出前授業」について
- “先生”体験から考える
豊かな言葉を引き出す仕事――新聞はもっと教育に貢献できる
「いくら小説を書いても、まるで暗闇に向かって石を投げているようです」
7年ほど前のこと。鎌倉に暮らした劇作家・小説家の井上ひさしさんが、ふと漏らした言葉です。自作がどれほど読まれているのか、手応えが感じられないということなのでしょう。こうした思いからなのか、井上さんは晩年、演劇にエネルギーを注ぎました。観客とじかに向き合う舞台は、演じる者と見る者の間に心地よい緊張感があります。
それから活字離れはさらに加速し、とりわけ若年層に顕著です。NIE事業に携わっていると、小学校では、新聞を購読している家庭が3割ほどのクラスまであるという話を耳にします。児童どころか、本や新聞をあまり読まない教職員も多くなった時代です。
しかし私は最近、小学生や中学生と関わる機会を得て、ある希望の萌芽を見つけることができました。子どもたちの中にはしっかりした言葉が宿っており、それを引き出す作業を大人が怠っているだけではないのか、という思いを抱いたのです。
次のページ >> 記者は「厳しくて地味な仕事」