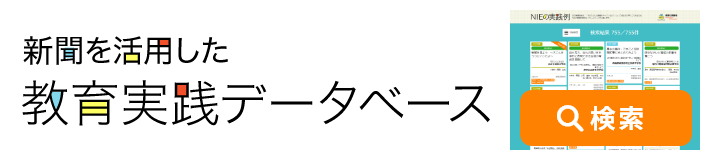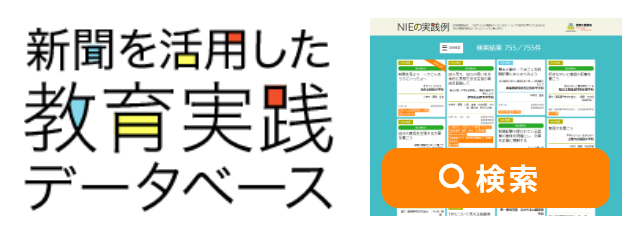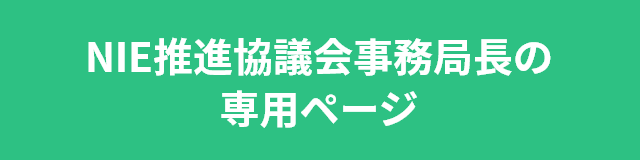日本新聞協会はNIE全国大会を毎年開催しています。同大会は、NIE実践者およびNIEに関心をお持ちの先生方と新聞社のNIE担当者を対象に、先生同士の経験交流、先生方と新聞関係者との情報交換の場を提供することを目的に実施しています。
NIE全国大会の情報は、こちらのページで順次お知らせします。
京都大会プログラム
| 大会スローガン |
探究と対話を深めるNIE デジタル・多様性社会の学びに生かす |
| 日程 |
2024年8月1日(木)、2日(金) |
| 主催 |
日本新聞協会 |
| 共催 |
京都府教育委員会、京都市教育委員会 |
| 主管 |
京都府NIE推進協議会、京都新聞社 |
8月1日(木)[全体会] 会場 ロームシアター京都(敬称略)
| 開会式 |
|
| 基調講演 |
「刷り物の字が教えた日本」
磯田道史(歴史家、国際日本文化研究センター教授) |
| パネルディスカッション |
「きょうを読み、あすを解く(NIEの歴史と可能性)」 |
8月2日(金)[分科会] 会場 京都経済センター
| 公開授業・実践発表 |
京都市立御所南小学校、京都市立羽束師小学校、AIC国際学院京都初等部、京都教育大学附属桃山小学校、京都府立聾学校、京都市立西京高等学校附属中学校、京都女子中学校、京都市立開建高等学校・塔南高等学校、京都先端科学大学附属中学校高等学校、綾部市立八田中学校、京都府立東宇治高等学校、亀岡市立詳徳小学校、八幡市立男山東中学校 |
| 特別分科会 |
「子ども新聞、子ども記者活動」「京都のNIE史」
|
| ポスターセッション |
|
| 閉会式 |
|
※大会終了後、全国NIEアドバイザー会議を開催
過去の全国大会(敬称略)
| 大会スローガン |
ICTでひらくNIE新時代 |
| 記念講演 |
「いのちを守る ことばを育てる」
夏井いつき(俳人、俳句集団いつき組組長、松山市在住)
|
| 基調提案 |
馬越吉章(愛媛県NIE推進協議会会長、NIE全国大会松山大会実行委員会会長、愛媛県小中学校長会会長、今治市立南中学校校長)
|
| パネルディスカッションのテーマ |
ICTでひらくNIE新時代 |
| 参加人数 |
1,200人 |
| 大会スローガン |
いまを開き 未来を拓く NIE |
| 記念講演 |
「リチウムイオン電池が拓く未来社会」
吉野彰(旭化成名誉フェロー、2019年ノーベル化学賞受賞者)
|
| 基調提案 |
田上幸雅(宮崎県NIE教育推進委員会委員長・宮崎市立生目南中学校校長/日本新聞協会NIEアドバイザー)
|
| パネルディスカッションのテーマ |
NIEで伸びる力、伸ばす力~子どもたちを持続可能な未来の創り手へ~ |
| 参加人数 |
1,100人 |
| 大会スローガン |
新しい学びを創るNIE~家庭、教室、地域をむすぶ~ |
| 基調講演 |
「歴史と出会う—新聞という回路」
梯久美子(ノンフィクション作家)
|
| パネルディスカッションのテーマ |
新しい学びを創るNIE~家庭、教室、地域をむすぶ~ |
| 参加人数 |
1,217人(視聴申し込み数) |
| 大会スローガン |
ともに生きる 新聞でつながる |
| 基調講演 |
「社会の声をつむぐ小説 伝える新聞」
真山仁(小説家)
|
| パネルディスカッションのテーマ |
ウィズコロナ時代にNIEで培う力~ともに生き、つながるための資質・能力 |
| 参加人数 |
1,347人(視聴申し込み数) |
| 大会スローガン |
深い対話を育むNIE |
| 基調講演 |
「NIEの先達 大村はま―三つの実践例をたどりながら―」
苅谷夏子(大村はま記念国語教育の会事務局長、作家) |
| 基調提案 |
松本敏(宇都宮大会実行委員長、栃木県NIE推進協議会会長、宇都宮大学大学院教授) |
| パネルディスカッションのテーマ |
新聞で育む深い対話 |
| 参加人数 |
1,100人 |
| 大会スローガン |
新聞と歩む 復興、未来へ |
| 記念講演 |
「新聞力と復興」
齋藤孝(明治大学教授) |
| 基調提案 |
望月善次(盛岡大会実行委員長、岩手県NIE協議会会長、岩手大学名誉教授) |
| 座談会のテーマ |
新聞と歩む 復興、未来へ |
| 参加人数 |
1,600人 |
| 大会スローガン |
新聞を開く 世界をひらく |
| 記念講演 |
「世界を照らすLED~未来を照らすことの大切さ~」
天野浩(名古屋大学教授、ノーベル物理学賞受賞者) |
| 座談会のテーマ |
頭の知識 体の知識 |
| 参加人数 |
2,430人 |
| 大会スローガン |
新聞でわくわく 社会と向き合うNIE |
| 記念講演 |
「言葉に触れる、言葉で触れる」
小野正嗣(芥川賞作家、立教大学文学部教授) |
| 基調提案 |
堀泰樹(大分県NIE推進協議会会長、大分大学教育学部教授) |
| パネルディスカッションのテーマ |
楽しくなければNIEじゃない! ~私たちはなぜ新聞活用に取り組むのか その意義と実践のこつ~ |
| 参加人数 |
1,423人 |
| 大会スローガン |
「問い」を育てるNIE~思考を深め、発信する子どもたち~ |
| 記念講演 |
「『今を生きる力』を育てる新聞~40年間にわたる新聞活用実践を通して~」
尾木直樹(教育評論家・法政大学教授) |
| 基調提案 |
「新聞と教育の緊密なかかわりは必然―21世紀型学力と民主主義」
阿部昇(秋田県NIE推進協議会会長、秋田大学教育文化学部教授) |
| パネルディスカッションのテーマ |
NIEで豊かな「問い」をどのように育てるか |
| 参加人数 |
1,000人 |
| 大会スローガン |
よき紙民になる―子どもに意欲を持たせるNIE活動 |
| 記念講演 |
「『賢い市民』と教育」苅谷剛彦(英・オックスフォード大学 教授) |
| 基調提案 |
「親しむ」ことから「学び」を広げる
原卓志(徳島県NIE推進協議会会長、鳴門教育大学教授) |
| シンポジウムのテーマ |
子どもに意欲を持たせるNIEの在り方 |
| 参加人数 |
960人 |
| 大会スローガン |
「学び」発見―ふじのくにから「やさしいNIE」 |
| 記念講演 |
「子どもたちへのおくりもの―豊かな心を育むために―」
山口建(静岡県立静岡がんセンター総長) |
| 基調提案 |
「発祥の地 静岡から、新たなステージに向かって」
角替弘志(大会実行委員長、静岡県NIE推進協議会会長、静岡大学名誉教授) |
| パネルディスカッションのテーマ |
NIEのすそ野を広げるために |
| 参加人数 |
1,375人 |
| 大会スローガン |
「考える人」になる いかそう新聞 伸ばそう生きる力 |
| 記念講演 |
「教育と福祉は出会えるか?―厳しい時代の中で、子どもの『生きる力』とは?」
湯浅誠(反貧困ネットワーク事務局長) |
| 基調提案 |
「子どもの歩みを踏まえ、学びをステップアップさせるNIE」
寺尾健夫(福井大会実行委員長、福井県NIE推進協議会会長) |
| パネルディスカッションのテーマ |
新しい時代に入ったNIE。何をどう、動くべきか |
| 参加人数 |
1,780人 |
| 大会スローガン |
読み解く力 新聞で ―学校・家庭・地域からNIE(エヌアイイー) |
| 記念講演 |
「『ことばの力』を身に付ける―急速に変化する世界だからこそ、立ち止まって考えよう」北川達夫(日本教育大学院大学客員教授) |
| パネルディスカッションのテーマ |
読み解く力 新聞で ―新学習指導要領とNIE |
| 参加人数 |
850人 |
| 大会スローガン |
学校から社会へ~学びを深め、暮らしに生きるNIE |
| 記念講演 |
「笑いのある人生」 桂歌丸(落語芸術協会会長) |
| パネルディスカッション(分科会プログラム)のテーマ |
小、中、校、各校種:新聞で伸ばす学ぶ力、生きる力~新学習指導要領とNIE
特別講座:学校図書館の課題と展望~新聞活用に向けて
高校・大学合同:新聞でつなぐ高校と大学の学び~高大接続の視点から
大学・社会人合同:社会人基礎力アップのための新聞活用~大学から社会へ |
| 参加人数 |
1,740人 |
| 大会スローガン |
わかる ひろがる つながるNIE |
| 記念講演 |
「命は人と人のつながりで守られる」鎌田實(諏訪中央病院名誉院長、医師、作家) |
| パネルディスカッションのテーマ |
NIE、身近に引きよせるために |
| 参加人数 |
1,030人 |
| 大会スローガン |
こどもが拓くNIE 地域に根ざす学び求めて |
| 記念講演 |
「生きる力を新聞で」山本一力(作家) |
| パネルディスカッションのテーマ |
新聞活用を通して育てる社会力──新しい教育課程とNIE |
| 参加人数 |
810人 |
| 大会スローガン |
学びあい 世界を広げるNIE(教育に新聞を) |
| 記念講演 |
「言葉の力」重松清(作家) |
| パネルディスカッションのテーマ |
NIEの魅力再発見 新聞を通して見えてきたもの |
| 参加人数 |
850人 |
第11回(水戸市2006年)
| 大会スローガン |
学校から家庭・地域へ広めようNIE |
| 記念講演 |
「活字の楽しみ」出久根達郎(作家) |
| パネルディスカッションのテーマ |
明日のNIEを考えよう~地域NIE・家庭NIEの展望 |
| 参加人数 |
860人 |
第10回(鹿児島市2005年)
| 大会スローガン |
広げよう 深めようNIE~豊かな学びを求めて~ |
| 記念講演 |
「薩摩藩の情報収集と倒幕、維新」原口泉(鹿児島大学生涯学習教育研究センター長、法文学部教授) |
| パネルディスカッションのテーマ |
熱討・NIE「これまでの10年、これからの10年」 |
| 参加人数 |
804人 |
第9回(新潟市2004年)
| 大会スローガン |
活字文化を大切に 発展させようNIE |
| 記念講演 |
「考える力 新聞が育む~小説『山本五十六』を執筆して~」工藤美代子(作家) |
| パネルディスカッションのテーマ |
子供が高まるNIE―地域や学校の連携を視野に― |
| 参加人数 |
1,095人 |
第8回(松江市2003年)
| 大会スローガン |
明日に生きる力はぐくむNIE~学校・家庭・地域とともに~ |
| 記念講演 |
「古代出雲の実像に迫る~新聞情報から読み解く」藤岡大拙(島根女子短期大学学長) |
| パネルディスカッションのテーマ |
NIE・こどもから大人まで~島根からの提案 |
| 参加人数 |
603人 |
第7回(札幌市2002年)
| 大会スローガン |
踏み出そう新世紀NIE~北の大地からの発信~ |
| 記念講演 |
「新聞から見えるもの」山口昌男(札幌大学学長、文化人類学者) |
| パネルディスカッションのテーマ |
多メディア環境の中でのNIE |
| 参加人数 |
512人 |
第6回(神戸市2001年)
| 大会スローガン |
21世紀をひらくNIE |
| 記念講演 |
「いくつかの言葉」阿久悠(作詞家、作家) |
| パネルディスカッションのテーマ |
高度情報化社会とNIE |
| 参加人数 |
542人 |
第5回(横浜市2000年)
| 記念講演 |
「仕事を通して見た現代」山田太一(脚本家) |
| パネルディスカッションのテーマ |
NIE活動はどう学校を変えていくか |
| 参加人数 |
523人 |
第4回(大阪市1999年)
| 記念講演 |
「教育と編集感覚」森毅(京都大学名誉教授、評論家) |
| パネルディスカッションのテーマ |
期待膨らむNIE──総合的な学習で「生きる力」を |
| 参加人数 |
552人 |
第3回(仙台市1998年)
| 記念講演 |
「教育改革とNIE」河野重男(東京家政学院大学長) |
| パネルディスカッションのテーマ |
NIEはいま―2002年の新教育課程に向けて |
| 参加人数 |
380人 |
第2回(広島市1997年)
| 記念講演 |
「新聞の読み方、読ませ方」古川薫(作家) |
| パネルディスカッションのテーマ |
「生きる力」をはぐくむNIE |
| 参加人数 |
365人 |
第1回(東京都1996年)
| 記念講演 |
「文字文化を受け継ぐことの意義」井上ひさし(作家) |
| パネルディスカッションのテーマ |
報道・取材と教育の現場-NIE運動の可能性を求めて- |
| 参加人数 |
256人 |