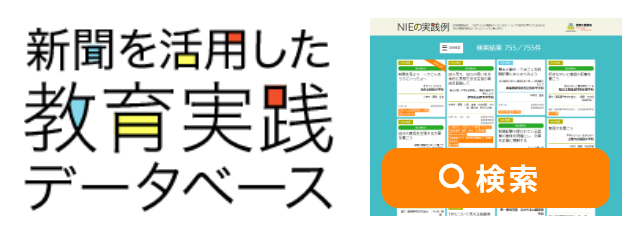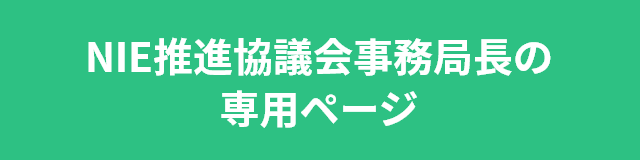実践指定校実践例 2014年度
複数の見出しをつけて、わかりやすく伝えよう!
| 大津市立膳所小学校(おおつしりつぜぜしょうがっこう) |
教科、科目、領域 |
小学校: 国語 |
|---|---|
| 学年 | 小学 4年 |
| 見出しと記事を対応させ、構成を工夫して新聞を作ろう |
| 見出しを活用することで、伝えたいことを明らかにしながら構成を工夫して書く力を育てる。 |
| 新聞に掲載されている写真を見て見出しを予想したり、記事を読んで見出しを考えたりする活動を通して見出しの役割や付け方を学ぶ。その後、複数の見出しを効果的に用い、見出しに対応する記事の構成を考えて新聞を作る。 |
1時限目
校外学習で体験したことや見聞きしたことを新聞にまとめるという活動の見通しをもつ。
2時限目
新聞の特徴を知る。
新聞社が発行している新聞を見て、特徴を見つける。
3時限目
見出しの付け方を知る。
4時限目、5時限目
記事や見出しを下書きする。
6時限目
わりつけを考えて、記事を清書する。
| 3時 |
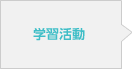 |
新聞に用いられている見出しを予想して考え、交流する。 |
|---|
 |
学習を通して、次のことに気づけるよう留意する。 |
|---|
これまでに、見出しを複数付けて書いたことがある児童は一人もいなかった。
新聞を作る際には、どの児童も二つ以上の見出しをつけて新聞作成に取り組んでいた。下書きを何度も読み直し、よく考えて見出しをつける姿も見られた。また見出しを決めた後で、下書きした記事の構成を変更する児童も見られ、見出しを意識することで構成に目を向けることができるようになっていった。
新聞記事の構成と対応させて見出しの学習に取り組んだことは、伝えたいことを明らかにし、構成を工夫して書く力を育てる上で非常に有効であったと感じた。とりわけ、複数の見出しをつける作業は、「一番伝えたいこと」と「その次に伝えたいこと」を順位づけることであり、自分の考えを整理したうえで書き始めることにつながった。複数の見出しをつけることは、普段子ども達が書いている日記にも応用した。つねに、何かを書く際に、二つ以上の見出しや題を考える場を設けることによって、構成を考えて書く力を高めていけると考えている。
実践者名:大津市立膳所小学校 廣田卓也