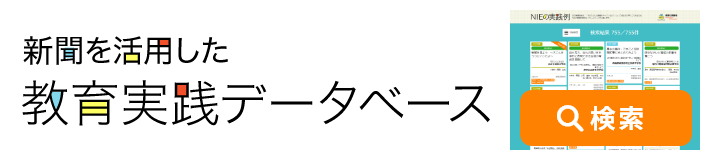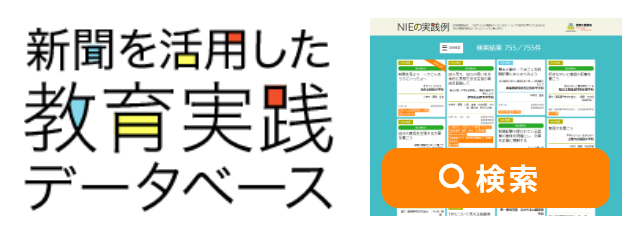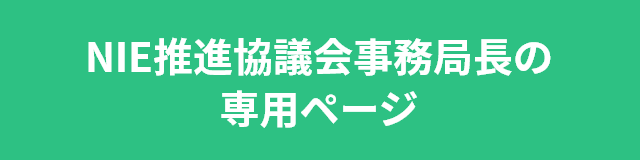NIE×STEAM教育 兵庫県NIE推進協が提案
- NIEトップ
- リポート NIEの現場から
- NIE×STEAM教育 兵庫県NIE推進協が提案
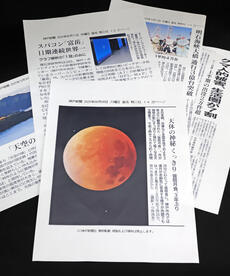
甲南小学校の教員研修で用いた新聞記事
兵庫県NIE推進協議会が、NIEとSTEAM(スティーム)教育を合わせた授業を提案している。最近の兵庫県内の話題を中心に、科学や工学、数学に関連する新聞記事を取り上げ、簡単な実験や実験動画の視聴、ワークシートなどを通して理解を深める。小学校などで実践してほしい取り組みだ。
STEAM教育は「科学」「技術」「工学」「芸術」「数学」の5分野を統合的に学び、実社会での問題解決能力や創造性を育む。AI時代に対応した次世代の教育とされる。
同協議会は記事を入り口にして、実験やワークシートに取り組んでもらう授業を考えた。2025年11月11日、教育方針のひとつにSTEAM教育を掲げる甲南小学校(神戸市東灘区)の教員研修で紹介した。教員約10人が参加した。
例えば、「皆既月食、兵庫でも3年ぶりに観測」(神戸新聞25年9月9日付)の記事から「月はすっぽり地球の影に入るのに、なぜ、赤銅色なのか」という問いを立て、光が真空から大気に入るときに屈折し、一部が月に届くことを学ぶ。真空をつくり出すのは難しいので、光が空気中から水中に入るときに屈折する実験を行う。
また、発想を転換し、5円玉を使って地球と月の距離を測ったり、実験を通して無重力で起きる現象を理解してもらったりする。
このほか、明石海峡大橋の車両通行台数の記事から「1日平均4万台が通るのに、なぜ、橋は壊れないのか」と問い、吊り橋の構造に関する実験動画を視聴する▽阪神間に横たわる六甲山から吹きおろす強い局地風「六甲おろし」の話題を起点として、人工的に風を起こす実験を行う▽明石市は東経135度の子午線が通る。子午線が通る他の市町を調べるとともに、子午線の長さ(4万9㌔)を割り出す実験を行う――などを提案した。
さらに、神戸市の理化学研究所計算科学研究センターで稼働しているスーパーコンピューター「富岳(ふがく)」が計算性能を示す国際ランキングの1部門で11期連続世界一になった記事(6月11日付)を読み、キーワード検索でスパコンの特長や成果を調べる取り組みを紹介。興味が深まれば現地見学することを勧めた。
NIEとSTEAM教育を合わせた授業のポイントは、最近の記事を取り上げる▽簡単な実験をする(難しければ実験動画を視聴する)――の2つ。今後、NIE活動と連動したプログラミング学習やAIを活用した授業も展開していく。
研修を受けた甲南小学校司書の田代弘子さんは「新聞記事を使うと、STEAMの学びが一気にリアルになる。実験を組み合わせると『知る』だけでなく『試す』楽しさが加わり、学びが動き出す。新聞が、子どもの探究心に火をつけるのでは」と話している。
三好正文(神戸新聞社NIE・NIB推進部シニアアドバイザー)(2025年11月25日)