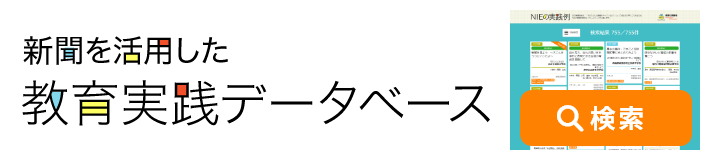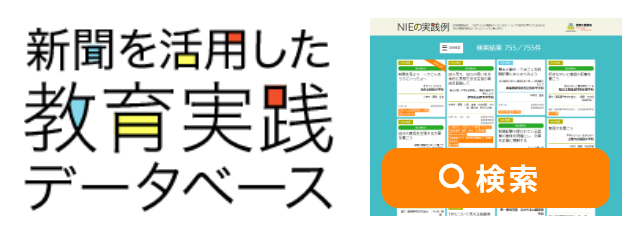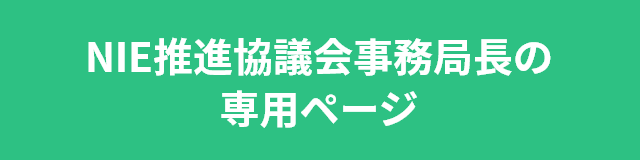神戸市の小学校、高校生に防災学ぶ
- NIEトップ
- リポート NIEの現場から
- 神戸市の小学校、高校生に防災学ぶ

大地震にどう備えるか――。
付箋を書いて模造紙に貼る小学生たち
=神戸市立横尾小学校
阪神・淡路大震災と能登半島地震の避難所生活を報じた新聞記事を教材に、高校生が小学生に防災でできることを伝える授業が2月5日、神戸市立横尾小学校であった。近くの兵庫県立須磨友が丘高校の生徒会役員12人が講師を務め、小学6年生45人と災害時の備えについて話し合った。
須磨友が丘高は日本新聞協会のNIE実践指定校で、横尾小での防災授業は3年目になる。これまでも阪神・淡路大震災当時、新聞各紙がどう報じたか――など、小学生とともに防災について考える取り組みを行ってきた。
この日の授業では昨年8月、能登半島地震の被災地で砂浜清掃などのボランティア活動をした寺尾凛太郎さん=須磨友が丘高2年=が、仮設住宅の写真などを見せながら現地の様子を報告。南海トラフ巨大地震への備えの重要性にも触れた。
続いて、数グループに分かれ、阪神・淡路と能登半島地震の発生から間もない時期の新聞記事を読み比べ、▽当時、避難所で困ったこと▽あなたなら避難所でどんな行動をとるか▽地震に備えて今から何をするか――などを付箋に書いて模造紙に貼っていった。
「防災バッグの中身を確認する」「避難経路を調べる」「ハザードマップを確認しておく」「ローリングストックをする」「地震が起きたときの待ち合わせ場所を家族で決めておく」――。小学生たちが付箋に次々と書き込んだ。
寺尾さんは「授業が、小学生に防災を自分ごととして考えてもらうきっかけになれば」、横尾小6年の土山康貴さんは「新聞を読んで避難所の状況を想像し、震災について真剣に考えた。ちゃんと備蓄できているか、家に帰って確認したい」と話した。
今回は、和歌山県NIE推進協議会の舩越勝会長(和歌山大学教育学部教授)が舩越ゼミの学生3人とともに授業を参観した。須磨友が丘高による近隣の小学校との防災の取り組みは、今年夏の「第30回NIE全国大会神戸大会」で発表され、舩越会長らが講評する予定。
◆担当された須磨友が丘高校・岩本和也先生の寄稿(授業のめあてや感想)はこちら
◆児童・生徒の感想はこちら
◆授業を参観した和歌山大生の感想はこちら(PDF)
三好 正文(兵庫県NIE推進協議会事務局長)(2025年2月14日)