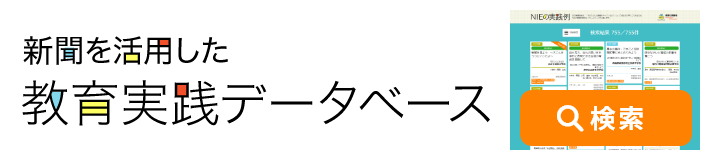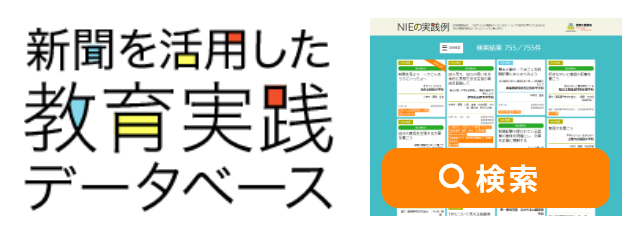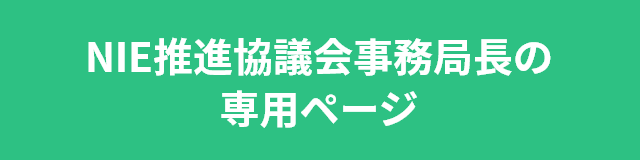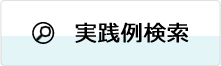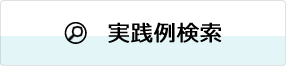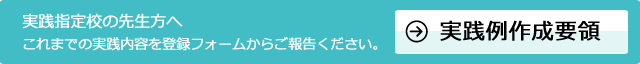新聞を活用した教育実践データベース
こども新聞「本の紹介コーナー記事」を活用した物語の授業実践 初心者向け
| 国立宇都宮大学共同教育学部附属小学校(こくりつうつのみやだいがくきょうどうきょういくがくぶふぞくしょうがっこう) |
実施年度 |
2019年度 |
|---|---|
教科、科目、領域 |
小学校: 国語 |
| 学年 | 小学 3年 、4年 |
| 使用教科書発行会社 | 東京書籍 |
| あらすじをまとめて紹介しよう!わたしの好きなこの一冊~はりねずみと金貨~ |
| いろいろ国や地域の本を人物の気持ちの変化や場面の移り変わりに注意しながら読み,選んだお気に入りの本のあらすじをまとめて紹介することができる。 |
| 「こども新聞」各社に毎週掲載されるおすすめの本のコーナーの紹介文を基に、あらすじのまとめ方について学習し、ねらいの達成へとつなげる。 |
第1次 教師の書いた紹介カードや子ども新聞の記事に掲載されている本のあらすじを読んで学習の見通しを持つ。外国の物語を読む。(1時間)
第2次 新聞に掲載された本の紹介文を参考にしながら教科書教材や選んだ本のあらすじを書く。(6時間)
第3次 書いたあらすじを基に選んだ物語を紹介し合い、感想を交流する。(1時間)
| 4時間(全8時間) |
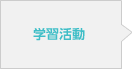 |
(1)前時に書いた教科書教材のあらすじのお試しを読み返したり、友達に読んでもらったりしながら感想を交流する。 |
|---|
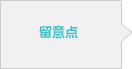 |
本単元でどんなあらすじを子どもたちに書かせたいのか(どんな読みの力をつけたくて、どのようにあらすじとして表出させたいか)を授業者がよく考え、新聞記事を選定する。 |
|---|
新聞記事に紹介されている物語のあらすじはプロの方が書いた紹介文であり、実際の本の表紙や見出しも掲載されているので、子どもたちは「この本読んでみたい」と興味深々であった。さらに、自分自身もこんな風に好きな物語のあらすじを書いてみたいという思いが生まれ、主体的に学習に取り組んでいた。
〈成果〉子ども新聞に掲載されている本の紹介文(あらすじ)は,児童の読書意欲を掻き立てる文面や紙面構成(イラスト・小見出し)となっている。提示することで,「この本読んでみたい!」という思いを生み,結果「自分が選んだ本のおもしろさをあらすじで友達に教えたい!」という思いに繋がった。このような新聞による学びへの主体性や目的意識の生成が,身に付けさせたい力(要約や場面の移り変わりに注意しながら読む力)の育成に向けた原動力となった。
〈課題〉提示した子ども新聞の記事「マッチ売りの少女」の絵本や文章と比較する活動を設けるなどしてあらすじのポイントについて話し合うと,考えがより深まったのではないか。過去に学んだ物語のあらすじの記事などを提示するのもよいと思った。
実践者名:国立宇都宮大学共同教育学部附属小学校 綱川 真人