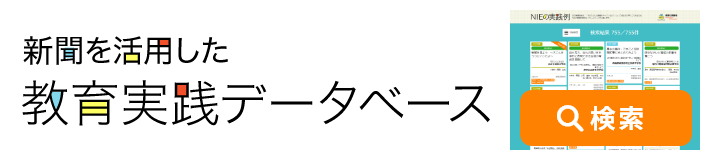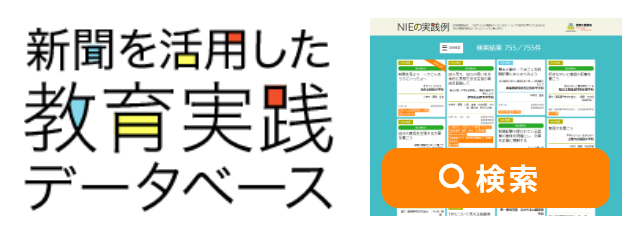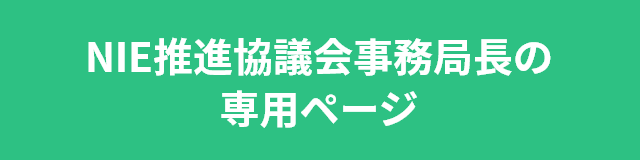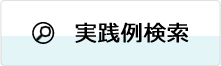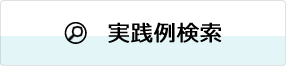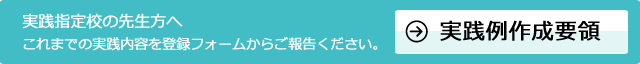新聞を活用した教育実践データベース
意見文を書こう
| 上越市立稲田小学校(じょうえつしりついなだしょうがっこう) |
実施年度 |
2015年度 |
|---|---|
教科、科目、領域 |
小学校: 国語 、総合学習 |
| 学年 | 小学 6年 |
| 使用教科書発行会社 | 光村図書 |
| 未来がよりよくあるために |
| 集めた情報を整理し、話し合いで深めた考えをもとに、構成を工夫して自分の意見を明確に伝える文章を書く。 |
| 新聞の投書欄には現代社会についての意見文が掲載されている。そこで、新聞を利用して読み手を納得させる工夫を学んだり、自分の考えの根拠としたりしていく。 |
単元の前半では、国語教科書資料「平和のとりでを築く」をきっかけにし、総合的な学習の時間の中で地域の「戦争」について調べ、新聞にまとめていく学習を行った。地域の過去や現在を知ったうえで、単元の後半には、よりよい未来に向けた意見文を書いていく学習を行った。意見文を説得力のあるものにするために新聞の投書記事を資料とし、「根拠となる事柄」を取り入れ、よりよい未来につなげるための意見文を書いた。
| 国語6 / 11 |
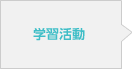 |
【新聞制作学習】 |
|---|
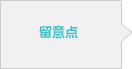 |
・子どもたちに身に付けさせたい力を意識して、教師が記事を用意することが必要である。 |
|---|
・教科書だけではなく、新聞の投稿記事に掲載された小中学生の文章を使ったことで、児童は自分と比較することができ、学習に関心をもって、積極的に取り組んだ。「有名な言葉を引用する」「資料のデータを使って述べる」「自分の体験を入れる」などの読み手を納得させる工夫を取り入れた意見文を全員が書くことができた。
・意見文(新聞の投稿記事)の文章構成や主張への根拠付けに着目し、読み手を納得させる意見文の工夫を捉えることで、自分の意見文に生かすことができた。
・書いた意見文は文化祭に展示し、地域の方から見ていただいた。意見文に自信をもつ子が増えた。
・記事を読んで考えを書いたり、話したりする活動を積み重ねてきたことで、自分の考えを表現する機会が増え、表現力の向上が見られた。
実践者名:上越市立稲田小学校 須山 哲也
NIEコーディネーターからのPICK UPポイント
国語の教材をきっかけに、総合の時間で「戦争」について新聞記事を資料として調べ、新聞を制作する。記事には効果的な見出しも工夫して入れる。また、実際の新聞の投書を手掛かりに、根拠を明確にした意見文を書き、記事の一つとして入れる。
⇒「戦争」に関わる記事を使った新聞活用を通して、新聞制作を行いながら、「投書」「コラム」などの要素を含む新聞の機能にも気付かせていく実践である。意見文の例として新聞の投書を使うことで、意見文としての具体的なイメージをつかんで学習することができる。
関口修司(日本新聞協会NIEコーディネーター)