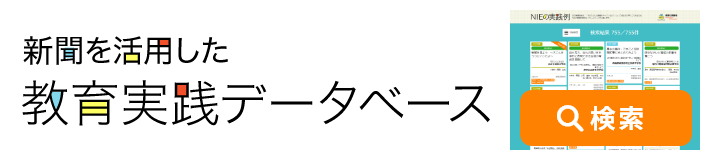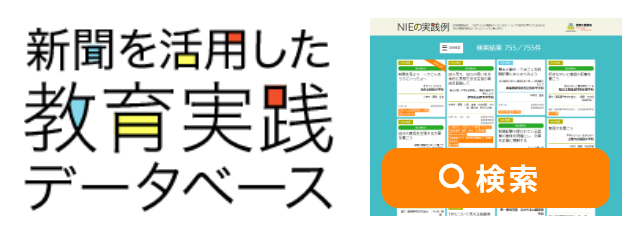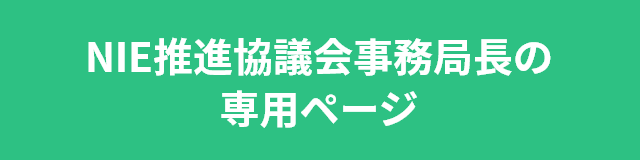先生向けページ
- NIEトップ
- メディアリテラシーを新聞で学ぼう!
- 先生向けページ
デジタル社会を生きる子供たちに今、最も求められるのは、偽情報や誤情報が入り混じったインターネットの大海から確かな情報を見極める力です。この力=メディアリテラシーを身につけるためには、新聞をはじめとする各メディアの機能・役割を知り、メディアによる情報の質の違いを吟味する学習が重要です。
では、実際にどのような授業が考えられるのでしょうか。
ここでは、授業やカリキュラムの中で、新聞を教材としたメディアリテラシー教育をどのように取り入れていくとよいのか、ヒントになるような実践や考え方を紹介します。
「動画・NIEはじめの一歩(メディアリテラシー編)」
新聞を使ってメディアリテラシー(情報を収集・選択・活用する力)をどう育むのか、その方法を示しながら、まずはフェイクニュースへの「免疫力」をつけることを推奨しています。どうすれば免疫力がつけられるのか、新聞と結び付けて解説しています。
第8回NIE教育フォーラム「学校教育におけるメディアリテラシー」
2025年3月に開催した標記フォーラムでは、ICTとNIE両方に精通した教育者と、新聞の正確な情報を支える校閲のプロを招き、メディアリテラシー教育の在り方や、批判的思考力の向上にNIEはどう寄与するのか――などについて議論を深めました。
当日の講演やセッションをこちらでお読みいただけます。

新聞を活用したメディアリテラシーの実践例紹介
情報を吟味し再構築する力の育成~生成AIを活用して~
- 単元名
- AIと社会のデジタル化
- ねらい
- 本実践は、既存のメディアリテラシーや情報リテラシーの枠組みを超えて、情報の受発信者である生徒が、多様な情報源を自律的に評価・統合し、デジタル社会における責任ある市民としての意識を育むことにある。これにより、個々の情報リテラシーの向上を目指す。
- 新聞活用のポイント
- 新聞は、伝統的な編集プロセスにより、情報が信頼性を有しており、情報(物事)の全体像や背景が容易に把握できる利点がある。その情報特性を生かしてデジタル情報と比較したり、批判的評価の基準としたりする。
- 具体的なポイントは以下の通り。
- ・基準としての活用
新聞記事は、厳格な確認・検証を経ているため、他のデジタル情報と比較する際の信頼できる基準となる。(裏取り、校閲等の意義を伝える) - ・情報の多層性の理解
情報の全体像や背景を把握しやすい特徴(紙面上での一覧性、情報の時間的推移)を持つ新聞と、断片的なデジタル情報との違いを明確にする。 - ・批判的思考の育成
新聞の記事内容や編集方針を分析することで、情報のバイアスや省略部分に気づき、批判的に評価する能力を育成する。(記事の論理的構成の理解、複数紙の読み比べの実践) - 学年
- 高等学校1年
- 教科・科目、領域
- 公共・公民科
実践内容
1限目「生成AIによるニュースの変容」
新聞記事・ネット記事・AI生成の記事の3種類を提示し、AIが生成した記事を考察する。また、生成AIのデモンストレーション(後述の学習活動(2))からニュースの違いを比較検討する。
2限目「フィルターバブルによるバイアスの理論的理解」
フィルターバブル体験のワークショップを実施する。生徒が日常的に接するニュースの傾向や各自が収集した情報の事例を共有し、バイアスの仕組みについて理解する。
3限目「情報再構築能力の育成」
異なる視点のニュースを比較し、共通点・相違点を整理することにより、情報を生徒自身が自律的に再構築することで多角的な理解を深める。
- 時
- 3時間
- 学習活動
(1)「ニュースは本物か?AIニュースクイズに挑戦」と題してAIが生成したニュースと人間が書いたニュースの違いを見破れるかという課題に挑戦する。AI生成記事については、新聞記事やニュースなどから得た情報を生成AIに読み込ませた上で「新聞記事のような形式で出力してください」と指示を出して作成する。
(2)教員が生成AIを用いて、同一のニュースを異なる視点(環境・経済・国際関係)から生成する過程をライブデモンストレーションし、生徒は生成AIが作成したニュースの違いを比較検討する。
(3)自身の情報源を振り返り、情報の偏りを感じられるかをフィルターバブル体験のワークショップで体験し、取り組みを通じた考えの変化を自身の言葉でアウトプットさせる。手順は以下の通り
①太陽光発電と蓄電池の普及について全員に同じ記事を読ませる。
②「環境保全を重視」「経済成長を重視」という異なる視点で書かれた記事について、教室の列ごとに2本のいずれか一方を読ませ、感想を記録する。
③異なる立場の記事を読んだ隣の列とグループを作ってディスカッションを行い、感想にどのような変化があったかを話し合う。
④「上記①の記事を読んだ後」「②の記事を読んだ後」「グループディスカッションの後」それぞれの考えの変化を確認し、記録する。(4)生徒が自分のスマートフォンやPCでおすすめされた情報などを基に収集したニュースを発表し、各グループで意見をまとめて見解を共有する。
(5)集めたニュースについて、「事実報道と批判・意見記事」「国内メディアと海外メディア」「政府の視点と市民の視点」「科学的、感情的、倫理的それぞれの視点」など、記事の特性を踏まえて分析させる。
(6)これまで学習したことを踏まえ、これからどのようにニュースと向き合っていくかをアンケートに記入する。
- 留意点
- ①生徒に分かりやすい違いがみられるように指導者側が配慮し、題材を提示する。
②当該の記事全体を見せるのではなく、授業のポイントに関連する部分に絞って見せることで生徒がテーマに集中できる。
生徒の反応
「これまで何の疑いもなく、流れてくる情報を受け取っていた」「知らない間に自分もバイアスがかかっていたんだなと思った」などの自身の情報受容の仕方を振り返る意見に加え、「生成AIが進化すると見分けつかなくなるのかな」「AI主導で世の中が動いていくのかも?」などの意見も見られた。
実践の成果と課題
生徒は、従来の受け身な情報受容から脱却し、提供されたニュースや情報を、新聞記事に代表される信頼性の高い情報によって培われた自らの背景知識や文脈と照らし合わせ、積極的・批判的に評価・統合する姿勢を示している。具体的な成果としては以下の点が挙げられる。
①実践を通じて、生徒は従来の情報収集から分析、アウトプットに至るまでの時間が短縮され、認知処理の効率が向上した。
②アウトプットにおける論理的な矛盾や情報の欠落が減少し、精度が高まることも確認できた。
③情報の多層性や偏りに気づくとともに、学習活動(1)(2)を通じて各情報源の信頼性を比較することで柔軟な思考が育成された。
④ワークショップやディスカッションを通じて、単に知識を受け取るのではなく、自分自身の視点で情報を再構築し、デジタル市民としての自覚と責任感を持つようになった。
これらの成果は、メディアリテラシー教育における「批判的思考力」と「自律的な情報再構築能力」の向上を反映している。
今後の課題としては、ニュースの情報源を多角的にチェックする習慣を身に付けさせると同時に、AIツール利用時の倫理と安全性について再確認することが挙げられる。
また、指導者側においても多様なデジタル情報環境に対応するための指導方法や技術面での改善が必要となる。
実践者名:東京都立練馬高等学校教諭 小松 純
教育実践データベースでは、メディアリテラシーに関する全国の事例を公開中です。
こちらよりご覧ください。