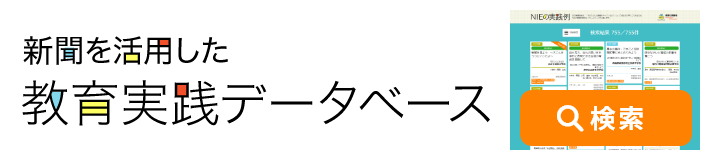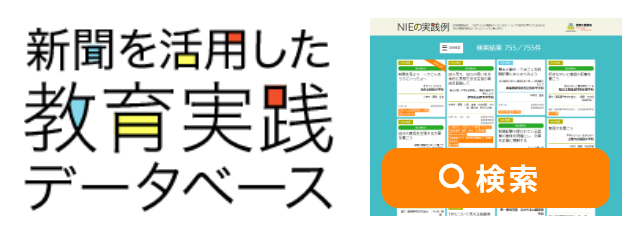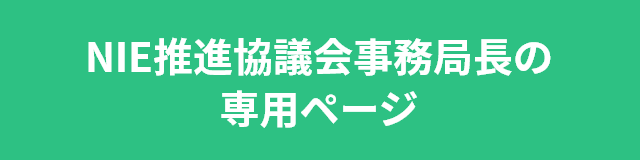メディアリテラシーを新聞で学ぼう!
- NIEトップ
- メディアリテラシーを新聞で学ぼう!
メディアリテラシーとは

情報を有効活用し、偽情報や偏った情報から身を守るために欠かせない能力がメディアリテラシーです。メディアの特性を理解したうえで、情報を「収集・吟味・選択・加工・発信・交流」する力とも言えるでしょう。
デジタル空間には、「信頼できる情報」から「根拠のない情報」や「悪意のある情報」までが混在しており、その見極めは非常に難しいものです。SNSの普及により、人々にとって情報伝達が「共有して理解を深める」ものから「煽(あお)って反応を集める」ものへと変化しつつあることも懸念の一つです。
メディアリテラシー教育の目標は、感情や物語(ナラティブ)に流されず、正確な情報を見極め、理性と論理に基づく議論を重視する姿勢を養うことにあります。
新聞は、丹念な取材から得た事実に基づく情報を日々発信し続けています。このページでは、メディアリテラシー教育を考えるうえでNIEが果たせる役割について紹介しています。
なぜ大切なの?
SNSの隆盛に伴い、情報の【公正さ・正確性・責任】という価値が軽視される風潮があります。メディアリテラシーが重視される理由です。
メディアリテラシー教育とNIEの関係性を図示してみました。
※関口修司・日本新聞協会NIEコーディネーター作成
メディアによるニュースの質の違い
正確性が命=新聞

新聞社のニュース発信は、記者の取材から始まります。事件・事故の現場に行ったり、関係者に話を聞いたり、関連資料を丹念に読み込むなどして正確な情報を集め、それらの事実に基づいて記事原稿を書きます。
記者が書いた原稿は「デスク」と呼ばれるベテラン記者による厳しい確認作業を経て、レイアウトを担当する整理記者に送られます。整理記者は原稿を読んで見出しを付け、パソコン上で本文や写真などを割り付けます。

原稿はさらに、記事のミスを防ぐ「最後のとりで」と呼ばれる校閲記者が細かくチェックします。①誤字脱字はないか、言葉遣いは適切か、②事実関係に誤りはないか、③わかりやすく、配慮の行き届いた文章か――。多岐にわたる視点から、掲載にふさわしい内容かを点検して、ようやく記事として完成します。新聞社発のニュースは、丁寧な取材に基づく正確な情報をもとに書かれ、何重ものチェックを経て広く社会へ発信される、正確性の高い情報なのです。
手軽な受発信に潜むリスク=ネット情報

一方、インターネット上には新聞社発のニュース以外にも、根拠がはっきりしないものや、意図的に作られた偽情報など、さまざまな“ニュース”があふれています。
中でも、誰もが手軽に発信できるSNS上には、悪意ある書き込みや事実誤認、偏った考え方に基づく情報も少なくありません。しかし、多くの人が目の前に流れてくる情報の真偽や発信元を気にすることなく受け入れ、気軽に拡散しがちです。ある一つの事実を異なる立場から見たときに、同じ景色が見えるとは限りません。これを認識しないまま、一方の見え方だけを「正しい」と信じるのは、とても危険なことです。

新聞も、同じ事柄の報じ方や取り上げ方は新聞社によって異なります。しかし、いずれも事実に基づいた質の高い情報である点が強みです。複数の新聞記事を読み比べることで、一つの視点に偏らない幅広い知見が得られます。それこそが民主主義の証なのです。
*情報と新聞の体験型ミュージアム「ニュースパーク」(横浜市)では、確かな情報の大切さや、複数の情報を比べることの重要性を学ぶことができます。
◆ニュースパーク公式サイト:https://newspark.jp/permanent/society/

*多くの新聞社で、新聞記者らがゲストティーチャーとして学校に出向く「出前授業」を実施しています。「新聞の読み方」「記者の仕事」といったテーマでレクチャーしたり、取材体験ワークショップを行ったりしています。
詳しくは下記の紹介ページをご参照のうえ、新聞各社または各都道府県のNIE推進協議会にご相談ください。
◆新聞各社の「出前授業」について:https://nie.jp/demae/
全国の新聞社のゲストティーチャーの声や、模擬授業ムービーを公開中
◆各地のNIE推進協議会:https://nie.jp/orglist/
47都道府県で組織されている、地元の新聞社(総・支局、支社を含む)、教育行政、学校現場の各代表などによって構成されるNIE活動の拠点です
民主主義とメディアの役割・責任

情報を伝える媒体が「メディア」です。情報を受け取る人の思考や社会的活動、ひいては世論形成に影響を与えることから、メディア、特にマスメディアには公正さと正確性が求められ、社会的責任が伴います。
100社を超える新聞・通信・放送社が加盟する日本新聞協会がよって立つ新聞倫理綱領は、民主主義社会を支える国民の知る権利に応えるために、「あらゆる権力からの独立」「正確・公正な記事と責任ある論評」「言論・表現の自由を守る」ことを明記しています。
インターネットは双方向性、だれでも発信できる自由さ、幅広く膨大な情報量、即時性、広汎性が特徴の画期的なインフラ(社会基盤)です。しかし、様々なメディアが林立するネット空間では、匿名による誹謗・中傷、誤報・虚報が後を絶たず、責任の所在も不明確です。メディアの社会的責任には、責任の自覚と責任能力が欠かせません。
メディアの役割を理解し、各メディアの特性を知り、情報を吟味・評価して発信のモラルを身につけ、社会参画する力がメディアリテラシーです。そうした力を培う学校教育がますます大切な時代であり、NIEの役割は高まっています。
(赤池 幹・元日本新聞協会NIEコーディネーター)
有識者インタビュー(新聞協会「新聞科学研究所」サイトより)
新聞協会が運営するウェブサイト「新聞科学研究所」では、メディアリテラシーに関する有識者のインタビューを掲載しています。ぜひご覧ください。

注目を奪い合うアテンション・エコノミーに踊らされないために今からできること
人々の注目(アテンション)をいかに集めるかが経済的価値に直結する構造は「アテンション・エコノミー」と呼ばれ、SNSや動画サイトなどを中心に、私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。アテンション・エコノミーがもたらす社会的リスクや、偽情報が拡散される構造、そして社会における新聞の役割について聞きました。
慶応義塾大学大学院法務研究科教授 山本龍彦さん
読売新聞東京本社社会部記者 石浜友理さん

選挙の投票先どう決める?選挙情報の集め方3ステップと参考にしたい情報源
SNSや動画共有サイトの普及により、ネット上の情報が選挙の候補者や政党の印象を大きく左右することも少なくありません。情報があふれる現代においては、どの情報を信じ、どう判断するかが問われています。「ネット時代における選挙情報との向き合い方」について聞きました。
日本ファクトチェックセンター(JFC)編集長、ジャーナリスト 古田大輔さん

フェイクニュースがあふれる世界をどう生きる?情報との上手な付き合い方
誰もが情報を発信できるネットの情報空間には、フェイクニュースや真偽不明の情報があふれています。フェイクニュースの問題点や、膨大な情報が押し寄せる中での「情報との上手な付き合い方」について話を聞きました。
スマートニュースメディア研究所所長 山脇岳志さん