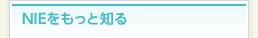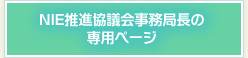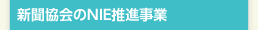“先生”体験から考える
- NIEトップ
- 新聞各社の「出前授業」について
- “先生”体験から考える
子どもたちこそが「先生」
40年を超える新聞社生活の中、私はほとんどを編集職場で過ごし、もちろん外勤記者も経験した。その中で、生徒たちが批判した「報道被害」や「ペンの暴力」をどこまで自分自身の問題として捉えていただろうかと、改めて考えさせられた。
新聞社、記者にはオピニオンリーダー、社会の木鐸としての務めがあり、時には巨大な権力にも立ち向かう勇気も必要だが、実は記者自身も本当は弱い人間で、いつも悩み、挫折を繰り返しながら仕事をしている。実際の新聞記者は、ドラマで演じられるほどカッコイイものではなく、「こんなはずじゃなかった」と現実に失望して新聞社を去っていった先輩や後輩もたくさんいた。だから、子どもたちから「どうしたら新聞記者になれるんですか」「新聞記者に向いているのはどんな人ですか」という質問を受けた時、私は「新聞記者も一人の普通の人間。信念を持って努力すれば誰でもなれる」と答えることにしている。
私にとっての新聞教室は、今までの記者生活をあらためて振り返る契機となり、本当にいい勉強をさせてもらっている。その意味では、子どもたちこそ私の「先生」だ。その子どもたちはと言えば、至って自分に正直だ。関心がある内容には明るく反応してくれるが、逆に講義がつまらなかったり、単調になったりすると、平気であくびをし、揚げ句は居眠りを始める。講師の私としては何とか子どもたちの目をこちらに向けようと必死になる。「子どもたちに私の話は理解できただろうか」「自己満足になってはいないか」「詰め込み授業になってはいないか」。毎回自問自答するばかりだ。
次のページ >> 「楽しかった」のひとことを期待して